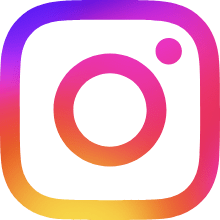肺がん
肺がんの検査方法
肺がん検査から確定診断まで
肺がんは、画像診断、組織診、細胞診などにより診断します。
肺がんが疑われる場合は、胸部X線検査や胸部CT検査などの画像検査を行い、腫瘍の位置や大きさを確認します。これらの検査で異常が見つかった場合は、検体を採取し、がんの特徴があるかどうかを顕微鏡で調べる病理検査(組織診や細胞診)を行い、診断を確定します。

「病気がみえるvol.4第3版p229」、「国立がん研究センターがん情報サービス 肺がん検診について」を参考に作成
肺癌では、確定診断後に遺伝子検査や病期診断→治療方針の決定を行います。
画像検査(※1)
画像検査はX線、磁気、超音波などを利用する検査方法で、がんの早期発見、治療方針の決定、予後(今後の病気の見通し)の予測などに重要な役割を果たします。画像検査には胸部X線(レントゲン)検査、CT検査、MRI検査、PET検査、骨シンチグラフィー検査、超音波(エコー)検査があり、患者さんの状態に合わせて、適切な検査法を選択・追加します。
胸部X線(レントゲン)検査
胸部全体にX線を当て、臓器のX線の通りやすさの違いを利用し、肺にがんを疑う白い影がないかどうかを確認する検査です。検査方法が簡便なため肺がん検診で行われます。
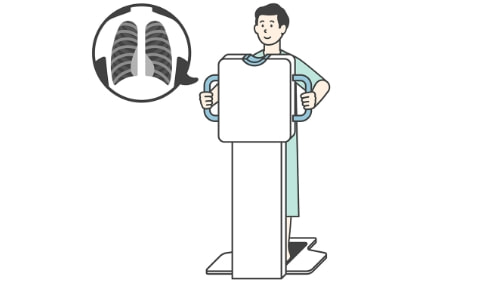
CT検査
体にX線を当て、得られた情報をコンピューターで解析する方法です。胸部X線検査ではわかりにくい体の深い部分の腫瘍も、位置や大きさを確認することができます。また、リンパ節転移や他臓器への転移の診断にも有用です。
MRI検査
強力な磁石の力を利用した検査で、体のさまざまな角度の断面を見ることができ、CTでは撮影しにくい部分も調べることができます。また、放射線を使用しないため、被爆の心配がないという利点があります。主に脳転移の検索のために行うことが多いです。
PET検査
がん細胞がブドウ糖をたくさん取り込む性質を利用して、ブドウ糖に似た薬(放射性ブドウ糖類似物質)を注射し、がんの位置を確認する検査です。これだけでは正確にがんを把握できない場合があるため、CTと組み合わせてPET/CTとして行われます。
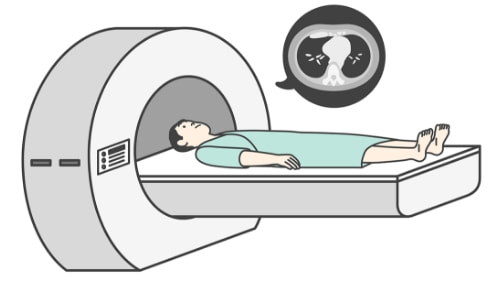
骨シンチグラフィー検査
骨にできたがん細胞に集まりやすい放射性物質を注射し、がんの骨への転移を調べる検査です。
超音波(エコー)検査
超音波を発する装置を用いて、体内の状態を観察します。胸水の検体採取時や肝臓や副腎への転移診断に使用されます。
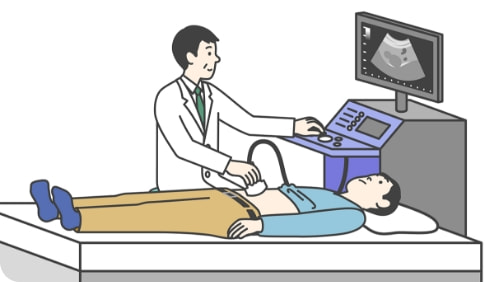
病理検査(組織診、細胞診)(※1)
画像検査では、「肺に影があり、がんが疑われる」ということしか証明できないため、確定診断には、がんが疑われる部位から細胞や組織を採取して、顕微鏡で詳しく調べる病理検査が必要です。それぞれの簡便さや侵襲性などを考慮して検査方法を選択します。
喀痰細胞診
痰の中のがん細胞の有無を調べる検査です。肺がんの確定診断の中で最も簡便な方法で、自ら痰を容器に出すだけで検査することができます。1回ではがんが検出されないこともあるため、数日分の痰を採取します。検診で行われることがありますが、近年、肺がん治療の個別化医療への変革から組織診断(しっかりとした組織の採取の重要性)の意義が高まり、あまり行われなくなっています。
気管支鏡検査・生検(※1、2)
気管支鏡は鼻や口から気道に挿入する内視鏡で、気管や気管支に存在する病変の観察や、検体採取に用いられます。目的に応じて、正常細胞とがん細胞の発光の違いをみる自家蛍光気管支鏡や、超音波検査と組み合わせた気管支腔内超音波断層法(EBUS)が行われることもあります。
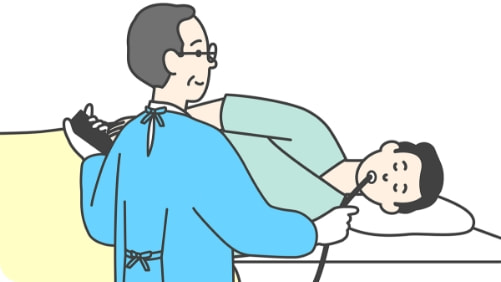
経皮針生検
皮膚の上から針を体内に挿入して検体を採取する方法です。X線透視やCT、超音波と組み合わせて行います。

胸腔鏡検査・胸膜生検
胸を小さく切開して、内視鏡を用いて胸腔内を観察する方法です。必要に応じて生検を行います。気管支鏡や経皮的生検で診断できない場合に行われます。
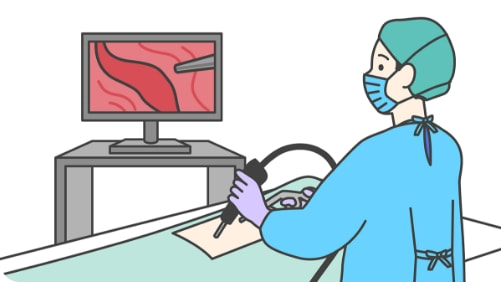
外科的肺生検
手術を行い、病変を目視や内視鏡で確認して検体を採取する方法です。体への負担が大きいため、他の検査法で診断がつかない場合に行われます。
腫瘍マーカー検査(※3)
腫瘍マーカーとは、がん細胞が、がんの種類によって特徴的に産生する物質で、血液検査などで測定すると、がんの有無や種類の予測、治療効果のモニタリングなどに役立てることができます。しかし、腫瘍マーカー検査では、偽陰性(がんが有るにもかかわらず無いと判定されること)や偽陽性(がんが無いにもかかわらず有ると判定されること)になることもあり、肺がんを特定・検出することはできません。
非小細胞肺がんの腫瘍マーカーとしては、CYFRA21-1、CEA、SLX、CA19-9、CA125、SCC、TPA、小細胞肺がんの腫瘍マーカーとしては、NSE、ProGRPが使用されることがあります。(※4)
遺伝子検査(※1)
肺がんの発生や増殖にはいくつかの遺伝子の異常(遺伝子変異)が関わっており、現在はこうした遺伝子変異を標的として、多くの治療薬が開発されています。
遺伝子変異を標的とした治療薬を使用する場合、患者さんのがん細胞にその遺伝子変異がなければ効果は得られません。そのため、より効率の良い治療を行うために、あらかじめがん細胞の遺伝子検査を行い、個々の患者さんにどの治療法が適しているかを検討します。肺がんでは、EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子、BRAF遺伝子などの遺伝子検査を行います。(※3)
通常は、がんの確定診断を目的に採取した細胞や組織を用いて遺伝子検査を行います。
個別化医療と検査(※1)
これまでのがん治療は、がんに幅広く効果がある方法(手術、化学療法、放射線療法)が使用されてきました。しかし、同じ治療法でも、患者さんの体質などによって、効果が得られる人と得られない人、副作用があらわれやすい人とあらわれにくい人など、個人差がありました。
これに対して、近年ではがん細胞の遺伝子変異の検査を行うことで、患者さんのがんの特徴に合わせた治療を選択する「個別化医療」が進んでいます。
このページは、2021年2月現在の情報をもとに作成しています。
参考文献
- 大江裕一郎, 鈴木健司 編, インフォームドコンセントのための図説シリーズ 肺がん 改訂第5版, 医薬ジャーナル, 2017.
- 医薬情報科学研究所 編, 病気がみえる vol.4 呼吸器 第3版, 株式会社メディックメディア, 2018.
-
国立がん研究センター, がん情報サービス, 一般の方向けサイト 肺がん 検査
( https://ganjoho.jp/public/cancer/lung/diagnosis.html:最終アクセス2020年11月) - 日本肺癌学会 編, 肺癌診療ガイドライン2020年版, 金原出版.